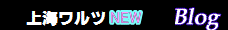昨日地下鉄10号線が虹橋空港まで開通したとのニュースを聞いて、「あること」を確認したくて仕事後に虹橋空港まで行ってきた。
「あること」とは虹橋空港第2ターミナルの地下鉄駅にある真ん中の大きなプラットホームのことである。
先日野暮用でこの駅に行ったときに、2号線のホームから覗けるこの中央の大きなプラットホームがとても気になった。
両側から列車に乗れるような構造になっていたのだが、手前が2号線でホームの反対側に見えたのが10号線であろうことは容易に想像がついた。
まあこれ自体は普通の駅の風景であるのだが、気になったのはこのホームにあった行き先表示板である。
実は2号線と10号線のホームが並んでいるにも関わらず、この真ん中に挟まれたホームの行き先表示板には「浦東空港」と「新江湾城」で、両側とも市内方向に向かう列車の乗り場表示になっていた。
空港から市内へ向かう客は同じホームで捌こうという目論見であることは想像に難くない。
しかしである。
2号線と10号線を地図上で確認する限りでは、この両方の行き先駅の方角は、虹橋空港から見て東側ということであるから、恐らくこのホームに停車する両側の列車は同じ方向に向かうことになる。
そしてその中央ホームの向こう側に標準タイプのホームがあり、その向こう側にも列車が止まれる構造になっているようであった。
恐らく10号線の逆方向の列車、つまり西の虹橋火車駅へ向かう列車の乗り場である。
とすると、、中央の2線は東へ向かう列車、外側の2線が西へ向かう列車用という構造ということになる。。。。
あれれれ?
そう、鋭い方はお分かりかと思うが、この構造では10号線は上下線が逆で、通常右側通行が常識の中国の鉄道において、この10号線は左側通行の形を取ることになる。
幾らルール破りが日常茶飯事の中国とはいえ、上下線の左右を逆転させて地下鉄を左側通行させるようなそんな掟破りが行われるのであろうか?
そこを確かめたくて今晩わざわざ行ってきたのである。
結論から言うと、10号線の今回開通した区間では、予想通り掟破りの左側通行が行われていた。
真ん中の大きなホームはまだ供用を開始していなかったが、10号線の中央側の線は東の市内方向に向かう列車用だった。
つまり10号線では左側通行で運営していることになる。
そして虹橋火車駅まで10号線に乗って確かめてみたが、この左側通行の区間は続いていた。虹橋火車駅のホームも左側通行の構造であり、通常の地下鉄とは逆方向に列車が停車する。
さらにこの左側通行がどこまで続いているのか気になって市内方向へ10号線に乗ったところ、上海動物園駅で通常の右側通行の配置の駅になった。
どうやら第1ターミナル駅と上海動物園駅の間に「ひねり」が入って上下線の配置が入れ替わっているらしいことが判明した。
この左側通行、幾ら地下鉄だから周囲や対抗列車があまり見えないとはいえ、運転士などは気にならないのであろうか?
人間的感覚から言えば、この上下線入れ替えのひねりはかなり違和感があると思うのだが、いずれ無人運転も計画されている地下鉄10号線である故に、人間的な感覚は些細なこととして扱われているのかもしれない。
ただ、乗員はそれでよいかもしれないが乗客にとってはちょっと厄介であり、慣れで行動してしまうと間違った方向の列車に乗ってしまう可能性を孕んでおり、そういった意味ではあまり人に優しくないのがこの10号線のような気がする。